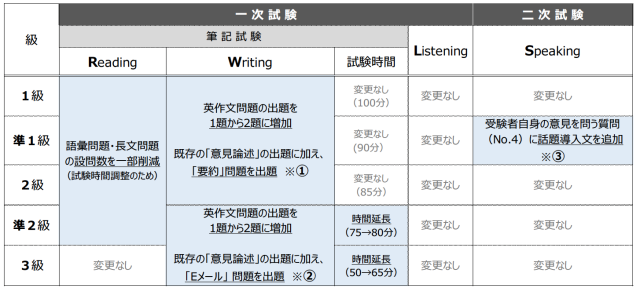子どもの教育格差の解消に取り組む公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン(東京・墨田区、代表者:今井悠介・奥野慧)は、家庭の経済格差による子どもの「体験格差」解消を目指し、全国各地で活動するNPO団体等と協働して子どもの体験機会を届ける「子どもの体験奨学金事業『ハロカル』」を全国に展開する。
この事業は、生活困窮世帯の小学生を対象に、スポーツや文化芸術活動、キャンプ等の参加費として利用できる「ハロカル奨学金」(=電子クーポン)を提供するとともに、地域で活動するNPO団体等と連携しながら子どもたちを地域の体験活動の機会に繋ぐ取り組みだ。初年度は、東東京(墨田区など)・沖縄・岡山・石巻の4エリアで事業を実施する。
CFCでは、「子どもの体験奨学金事業『ハロカル』」の展開に伴い、2023年度から2025年度までの3年間で1,000人の小学生への「体験奨学金」提供を目指すべく、クラウドファンディング(目標金額:2,000万円)を7月4日~8月31日の期間に実施する。
■低所得世帯の子どもの約3人に1人が、1年を通じて学校外の体験が「何もない」
CFCでは、2022年10月に全国の小学生保護者2,097人を対象に、子どもが学校外で行うスポーツや文化芸術活動、キャンプ、旅行等の「体験活動」への参加状況や年間支出状況等について、全国で初めての実態調査を実施した。
調査の結果、世帯年収300万円未満の低所得世帯の子どものうち、約3人に1人(29.9%)が、1年を通じて学校外の体験活動を「何もしていない」ことがわかった。学校外の体験活動を「何もしていない」子どもの割合は、世帯年収600万円以上の家庭(11.3%)と比較すると約3倍の差が生じている。
子どもの学校外の体験活動にかける年間支出においては、世帯年収300万円未満の家庭と世帯年収600万円以上の家庭との間に2.7倍の差が生じていることが明らかになった。また、子どもがやってみたいと思う体験をあきらめた理由としては、世帯年収300万円未満の家庭においては「経済的な事情(56.3%)」との回答が半数以上に上る。その他の重要な要因としては、「時間的余裕がない(51.5%)」、「近くに参加できる活動がない(26.6%)」「精神的・体力的余裕がない(20.7%)」などが挙げられ、体験活動をあきらめる上で多様な背景があることが窺える。
さらに、7月4日に公表した本調査最終報告書では、以下のことが明らかになった。
(1)子どもの体験活動に対する支出の格差は、家庭の経済状況だけでなく、様々な家庭背景(世帯構成、親の学歴、居住地域など)からも生じている。
(2)体験活動の分野別では、定期的な「スポーツ・運動」への参加率で、家庭の経済状況による格差が最も大きく表れているほか、定期的な「音楽活動」についても世帯年収による格差が大きい。また、キャンプ等の「自然体験活動」への支出において、三大都市圏に居住する年収600万円以上の家庭の支出が突出して大きい。
(3)低所得世帯の中でも、保護者が小学生の頃に体験活動に参加していない家庭では、直近1年間で子どもの体験活動が「何もない」割合が高く、半数以上(58%)にのぼった。
(4)体験活動は、企業やNPO等の民間事業者のほか、地域や保護者によるボランティア等、多様な担い手が存在する。また、居住地域によって体験活動の担い手の傾向が異なる。
※詳細は「子どもの『体験格差』実態調査 最終報告書」(2023年7月4日発行)を参照
子どもの体験奨学金事業「ハロカル」について
家庭の経済状況により生じている子どもの「体験格差」の実態を踏まえ、全国各地で活動するNPO団体等と協働して子どもの体験機会を届ける「子どもの体験奨学金事業『ハロカル』」を全国に展開する。
【事業の特徴】
特徴①:「体験活動」のための奨学制度
生活困窮世帯の小学生を対象に、スポーツや文化芸術活動、キャンプ等、子どもが「やってみたい」と思う体験活動の参加費として利用できる電子クーポン「ハロカル奨学金」を提供する。
特徴②:地域に根差した教室・クラブの参画
子どもたちが暮らす地域に根差して活動する教室やクラブ等に「ハロカル奨学金」の利用先として参画することで、運営事務局と地域の教室・クラブの先生方が、ともに子どもや家庭を見守る体制を構築する。利用先の教室・クラブは、子どもたちの希望に応じて随時追加していく。
特徴③:子どもと地域の教室・クラブを繋げる「地域コーディネーター」
「地域コーディネーター」が、家庭の相談に応じるとともに、子どもたち一人ひとりの興味関心や特性等をふまえながら利用先の紹介を行い、子どもと地域の体験活動を繋げる。また、自治体やソーシャルワーカー等と連携し、支援にたどり着きにくい状況にある子どもや家庭に情報を届けたり、必要に応じて家庭と支援機関を繋げたりする役割を担う(地域コーディネーターは、CFCと提携した各地域のNPO等が担う)。
子どもの体験奨学金事業「ハロカル」は、2022年度より、CFCの活動拠点である東京都墨田区を中心とした「東東京(運営:CFC)」や、2019年度に西日本豪雨の被災家庭向けに緊急支援を実施した「岡山(運営:特定非営利活動法人チャリティーサンタ)」の2地域においてトライアル事業を実施してきた。
この事業を全国に展開すべく、2023年度は東東京・岡山に加え、子どもの貧困率が全国で最も高い「沖縄(運営:CFC/協力:しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄)」、東日本大震災以降CFCが事業を展開してきた「石巻(運営:特定非営利活動法人TEDIC)」を含む4地域において事業を実施する。同時に、対象地域内での実施が難しいキャンプやウィンタースポーツ等の自然体験活動への参加を可能とする仕組みとして、全国で活動する自然体験活動団体のプログラム利用に対しハロカル奨学金を提供する「ハロカル・アウトドア」を一般社団法人日本アウトドアネットワーク事務局長の原田順一氏と連携しながら展開する。
また、2025年度までに全国10地域で延べ1,000人への奨学金提供を目指すほか、2025年度以降も事業展開地域を拡大していくとともに、全国の子どもたちに体験奨学金を届けていくため、政策提言を通じて全国に取り組みを広げていくことを目指す。
■3年間で1,000人への奨学金提供を目指し、クラウドファンディングを7月4日に開始
子どもの体験奨学金事業「ハロカル」では、個人や法人等からの寄付金を原資に、2023年度~2025年度までの3年間で全国延べ1,000人の小学生に「ハロカル奨学金」を提供することを目指している。2023年度中に総額1億円の資金調達を目指すべく、第一弾として、7月4日よりクラウドファンディングを実施する。
【クラウドファンディング概要】
◆WEBページ:
https://readyfor.jp/projects/halocal2023
◆実施期間:
2023年7月4日(火)~8月31日(木)
◆目標金額:
2,000万円
◆寄付金使途:
クラウドファンディングにより募った寄付金は、全額が「ハロカル奨学金」として子どもたちの体験活動の参加費用に使用される。