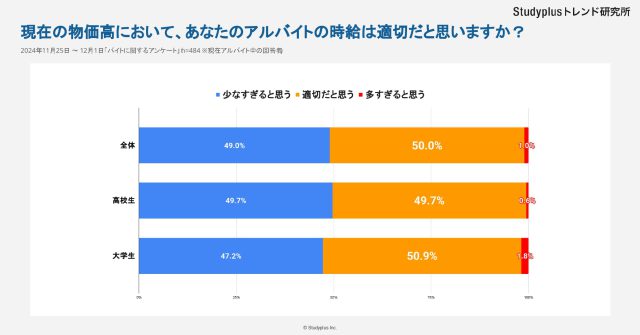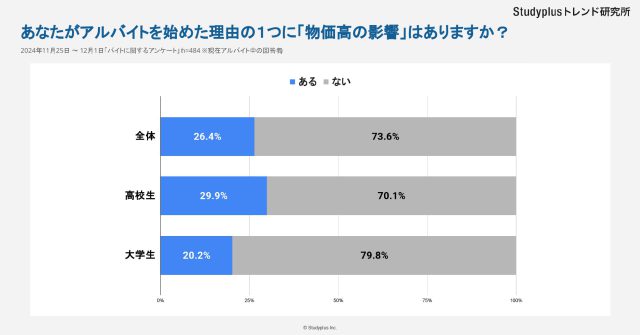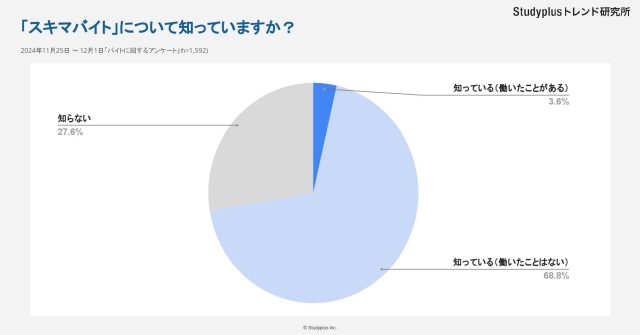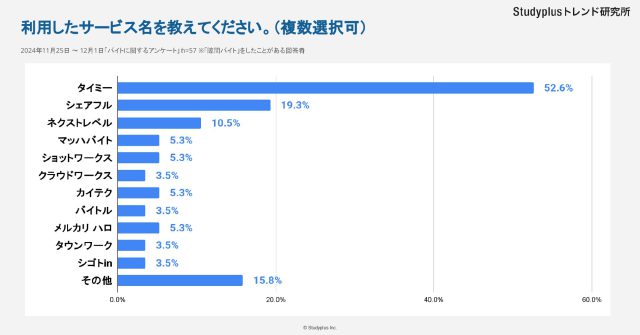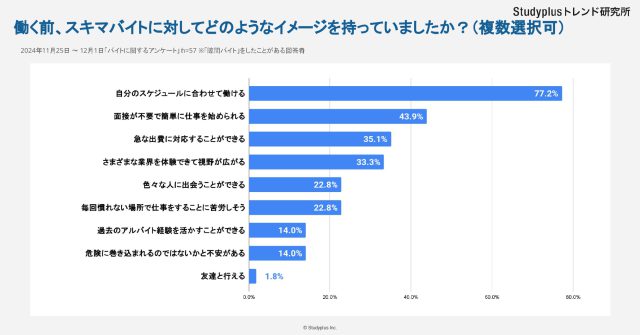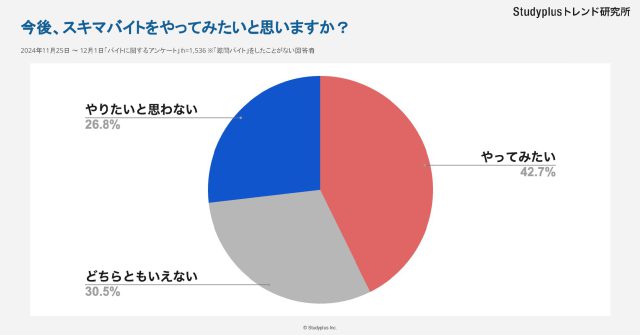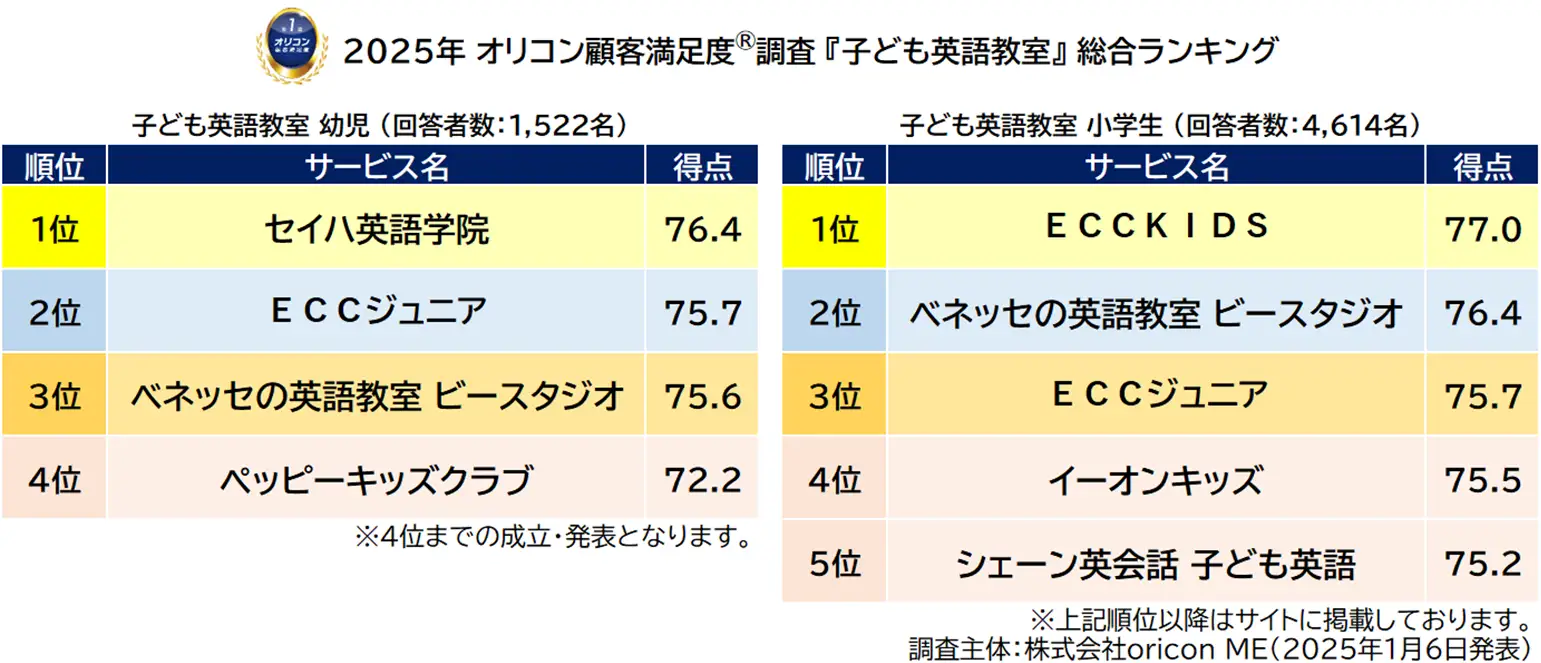株式会社スプリックス(東京・渋谷区、常石 博之 代表取締役社長)が運営するオンライン個別指導塾「そら塾」は、保護者のオンライン学習塾に対する意識を把握すべく、当塾保護者1,122名を対象にアンケート調査を実施した。
今回の調査では、昨今の共働き世帯の増加などの社会的背景が影響し、通塾・送迎時間や費用などのコスト面でのパフォーマンスを意識した塾選びが重要視されていることがわかった。また、オンライン学習塾の利用開始から1年以上経つ通塾者が全体の21%を占めており、86.8%の保護者が継続意向を示していることから、オンライン学習塾が塾選びの新たなスタンダードとして普及しつつあることが明らかになった。
【調査概要】
調査対象:そら塾に通う生徒の保護者1,122名(有効回答数)
調査手法:インターネット調査
調査内容:オンライン学習塾に対する意識調査
実施期間:2024年12月9日~12月20日
オンライン個別指導塾そら塾調べ
Topic1. 利用開始から「1年以上」が全体の21.3%を占める結果に!効率を求める時代の塾選びに「オンライン学習塾」の定着化が進む
オンライン個別指導塾「そら塾」の保護者を対象に、オンライン学習塾に対する意識調査を実施したところ、利用開始から「1年以上」という回答が全体の21.3%を占める結果に。今回の結果から、オンライン学習塾が新たな指導形態として注目を集めながらも、一過性の選択肢ではなく、長期的な学習パートナーとして定着している様子が伺える。特に、送迎不要で時間や場所を選ばずに学習を進められる効率性などが昨今のライフスタイルにあった価値観として受け入れられていることが伺える。
また、オンライン学習塾を利用する目的として最も多く挙げられたのが「定期テスト対策」と「学校の補習」であることから、受験前の短期的な利用よりも、定期テストや勉強習慣など日常的な学力の向上を目指すことを目的に利用するケースが多い傾向にあることがわかった。
Topic2. 86.8%がオンライン学習塾の利用を「続けたい」と回答!それぞれの生活スタイルと目的にあわせた塾選びが重要に
さらに、オンライン学習塾の継続意向について調査した結果、86.8%の保護者が「今後も利用し続けたい」と回答した。また、継続したい理由として「通塾・送迎が不要」という回答が最も多く挙げられ、送迎することに対して大きな負担を感じている家庭が多いことが明らかになった。その他にも「時間を有効に使える」「子どもに向いているから」などの回答も多く、共働き世帯が圧倒的に多くなっている中で、オンライン学習塾が昨今の生活スタイルにあった形態であることが伺える。
Topic3. 周囲の利用者増加を実感している割合は限定的な一方で、82.7%が「家族や友人にオンライン学習塾を勧めたい」と回答!
オンライン学習塾の利用者を対象に、周囲の利用状況に関する意識調査を行ったところ、オンライン学習塾を利用している人が「周囲で増えている」と感じた割合は17.7%と限定的だった。この結果は、オンライン学習塾の利便性や効果が実際の利用者以外に十分伝わっていないという点の他に、地方や一部地域ではオンライン学習塾というサービス自体の認知がまだ広がりを見せていない状況が伺える。
一方で、82.7%の保護者が「オンライン学習塾を友人や家族におすすめしたい」と回答し、高い満足度と推奨意向が伺える結果となった。これは、共働き世帯の増加や時間を有効的に活用したいというニーズが背景にあり、オンライン学習塾が塾選びの新たなスタンダードとして普及しつつあることが伺える。